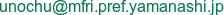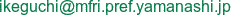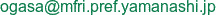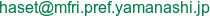| Mount Fuji Research Institute, Yamanashi Prefectural Government | |
 |
 |
| 富士山研について | 一般利用 | 図書室 | 教 育 | 研究紹介 | 広報と交流 | 刊行物 |
環境共生に関する研究分野
| 人と人をとりまく環境の関わりを明らかにし、富士山をはじめとする山梨の環境と人の関わりの意義の評価や、よりよいあり方の提案をめざして研究を行なっています。 |
| 宇野 忠 | 池口 仁 | 小笠原 輝 | 長谷川達也|
環境共生分野 スタッフ
 |
宇野 忠 UNO, Tadashi 博士(学術) 私達が囲まれている様々な環境要因、その中でも気象環境が生体機能に与える影響について研究しています。暑ければ熱中症の、富士山登山時には気温や酸素濃度、気圧変化にさらされ体調不良や高山病のリスクが上がります。このような問題にフィールド調査や実験室での動物モデル実験により取り組んでいます。 |
| 研究課題 |
科学研究費助成事業 基盤研究(C)
|
| 出張講義 | |
| 研究成果・研究活動 |
|
 |
池口 仁 IKEGUCHI, Hitoshi 計画学は計画プロセスの改善を目的とする実学の分野です。計画プロセスとは、期間を定めて、新しい知見を取り入れながらその期間に何をするかの合意を形成し、その時点でより良い社会を実現する手段をこうじ、結果を評価して次の合意形成につなげていく事を言います。計画学の中で造園・ランドスケープ分野は社会と自然の関係や、社会の中でのひととひとの「空間を媒介とする関係」を整理し、改善の手段を与え、評価する役割を担っています。 |
| 研究課題 | |
| 出張講義 | |
| 研究成果・研究活動 |
|
 |
小笠原 輝 OGASAWARA, Akira 住民と周囲の自然環境との相互関係の変化(特に里地・里山など)、生業の変化と環境の変化に対する住民の対応について研究をしています。 |
| 研究課題 | 基盤研究 |
| 出張講義 | |
| 研究成果・研究活動 |
|
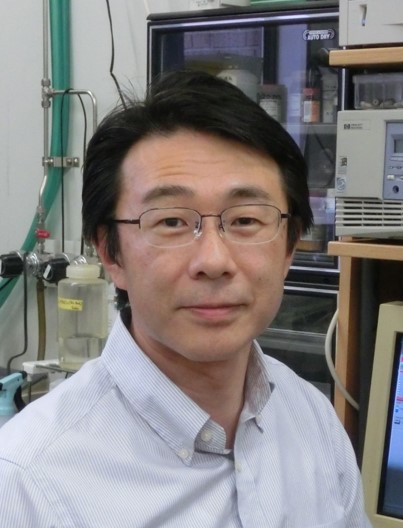 |
長谷川達也 HASEGAWA, Tatsuya 博士(薬学) 環境中に存在するミネラル成分(金属元素)の分析ならびにその健康あるいは生態系への影響について研究を行っています。特に、富士山周辺の地下水や湧水中に含まれる微量元素「バナジウム」の研究をしています。また、忍野八海やその周辺河川水の調査研究も行っています。 |
| 研究課題 | |
| 出張講義 | |
| 研究成果・研究活動 |
|
| 助 手 |
・瀧口(自然環境研究分野との兼務) ・塚田(自然環境研究分野との兼務) ・松山(自然環境研究分野との兼務) |